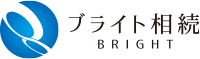「障害者控除」の適用で、相続税額を300万円以上減らした事例
通常、相続税の節税対策は被相続人の生前、元気なうちに計画、実行するのが一般的です。したがって、多くの相続人たちは、相続発生後に相続税を節税することはできないと考えてしまうようです。
しかし、実は、相続発生後でも手続きの進め方によって税額が大きく変わるケースがあります。今回は、相続税の申告手続を行った結果、相続税が当初想定よりも低くなった事例を紹介します。
長男が父親の財産すべてを引き継ぐはずだったが…
お客さまは、被相続人(亡くなられた方)がお父さま、相続人は長男、二男、三男の3名でした。ご兄弟のうち、二男が身体障害者手帳をお持ちで、障害の程度が2級とされていました。
当初の面談では、事業を引き継がれる長男がお父さまの財産をすべて引き継いで、今後の二男の生活や介護のお世話をするつもりとのことでした。二男も三男もこの方針に異議はなく、相続税申告その他の相続手続を進める方向で動いていました。
私たちは、ひとつのアイデアとして、「相続財産のうちの少額でも二男に引き継いでいただき、相続税の障害者控除を適用してはどうか」とご提案しました。結果として、ご家族全体の相続税が300万円以上減額されることになりました。
相続税の障害者控除の仕組み
では、「障害者控除」によって、どのように相続税が減額できたかをご説明いたします。
まず、相続税の「障害者の税額控除」は、相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができるというものです。
控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)につき10万円で計算した額です。
相続人が特別障害者の場合は1年につき20万円となります(特別障害者の定義についてはコチラをご参照ください)※1。
※1 なお、その障害者の方が今回の相続以前の、別の相続税申告においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されますのでご留意ください。
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる方です。
・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
障害者控除額が、相続税額より大きい場合は?
障害者控除を適用する際のポイントは以下二点となります。
(1)適用するためには障害者の方が少しでも財産を取得しなければなりません。
(2)障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者(※2)の相続税額から差し引きます。
※2 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
今回の私たちの提案は、当初長男だけが財産を取得するはずだったところ、あえて二男にも少額の財産を取得してもらい、障害者控除を適用するというものでした。それでも二男は少額の財産しか取得しませんので、二男単独でかかる相続税も非常に少額となります。
ただし上記(2)にあります通り、控除額を二男の相続税だけでは使い切れない場合、長男の相続税から差し引くことができるのです。結果として当初想定した障害者控除を使わない相続税額より、300万円以上減額することに成功しました。
このように、ちょっとした工夫で相続税額が大きく変わることがお分かりいただけたかと思います。税理士であれば誰でも知っているはずの「障害者控除」ですが、相続人の方たちの間で遺産分割方針が固まっている場合など、その適用が漏れることがあり得ますので注意が必要です。
今回ご紹介した「障害者控除」以外にも、相続発生後にできる工夫は多くありますので、相続税申告については、ぜひ相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史
お問い合わせ
-
安心・無料の相続相談はこちら
03-6261-7300
受付時間:9:00~21:00(土日祝日も対応)
-
24時間365日受付
無料相続相談
メールフォーム